
FinTechは社会のために。プロフェッショナルとしての挑戦
創業以来40年以上にわたりスモールビジネスの業務効率化と事業支援に向き合ってきた弥生。「弥生会計」を始めとした業務ソフトだけでなく、会計データに基づく与信エンジンの開発(ALTOA)といったFinTechサービスも開発・提供してきました。
その流れをさらに加速させるため、執行役員 FinTechイノベーション部長として2024年7月に弥生にジョインした小川は、キャリアの実に10年以上をFinTechに捧げるプロフェッショナルです。直近ではリクルート社での新規事業立ち上げも経験した小川が、弥生とFinTechにどのような可能性を感じたのかをインタビューしました。
▼他のインタビュー記事はこちら
執行役員 経営企画本部 FinTechイノベーション部長
小川 康秀
早稲田大学政治経済学部卒業後、京葉銀行入行。中小企業向け融資から大企業向けプロジェクトファイナンスの営業・審査を経験。2004年創業間もない楽天で楽天市場事業部長として、ITを活用した新規事業の立ち上げとネット銀行設立プロジェクトの責任者を務める。その後メーカーの経営企画室長、PEファンドの経営管理などを経て、2016年1月よりGMOペイメントゲートウェイで決済プロダクトの管理責任者およびFinTech領域の新規事業責任者、2022年1月よりリクルートのFinTech領域の新規事業立ち上げ・事業提携を担当。2024年7月弥生株式会社、FinTechイノベーション部長に就任。
FinTechという可能性に魅せられて
―まずは今までのキャリアについて教えてください。
大学卒業後、地方銀行からキャリアをスタートしました。銀行を目指したのは、実際に親族でお金をめぐるトラブルを目の当たりにした経験があるからです。私の父は5人兄弟で、経営者と公務員、郵便局の職員といった、様々な職業が混在しながらも、困ったときには助け合う、とても仲の良い兄弟だったと記憶しています。ところが、高校生の時にバブルの崩壊が見え始め、自動車整備業を経営する叔父の事業が傾き始めました。その結果、兄弟間でお金の貸し借りをすることになりました。すると、父を含めた叔父たちの関係性がとても悪くなっていったのです。それは当時強烈な印象を残し、自分が銀行員になり、お金の面からそうした中小企業経営者の課題を解決することで、彼らと同じような境遇の人を救えるのではないかと考えました。
入行してすぐに目指していた中小企業向け法人営業に就くことができたものの、自分自身が実際に経営者からTrusted partnerとして認められるレベルになるためには、多くの知識と経験が必要になると実感しました。具体的には経営者から信頼を得るためには財務面のアドバイスだけでなく、セールス・マーケティングや製造や仕入れといった広範な知識が必要であることに気づき、中小企業診断士の資格を取りましたが、実務でやるのが一番と思い、転職しました。
―企業選びで意識していたことはありますか?
審査業務にあたりながら、IT産業がものすごく伸びていることを肌で感じていたことと、当時担当していたリアルの商業モールからインスパイアされて、仮想商店街を運営する創業間もない楽天へ入社しました。“日本の中小企業をエンパワメントする”というビジョンを持っていたことも理由です。ここではIT産業の全体感を理解できましたし、UIUXと関連するシステム開発などの知識を得るとともに、高い成長市場で高い目標に挑戦することで自分自身の成長や戦友を作れたことが、今の仕事観にも繋がっています。
その後、同僚の家業である中堅メーカーへ経営企画として参画しました。経営企画だと全体的に会社を俯瞰できるのですが、未経験でしたので不安もありました。幸いにも、そこで出会った外資系企業で社長をやっていた方やグローバルで事業開発をしていた2人のシニアの方からは大きな影響を受けました。経営企画として様々なことを教えていただき、工場の海外投資プロジェクトも同時に複数マネジメントできたと思っています。そこからPEファンドで直接金融を経験し、多くの知見と推進力を身に着けました。2015年にデータのオープン化とFinTechの可能性が高まってきたタイミングで初心貫徹すべく、FinTechのコモディティ化を自分の天命と考え、GMOペイメントゲートウェイに入社し、そこから10年、FinTechという領域で奮闘することになります。
―親族という当事者、金融機関、FinTechサービスプロバイダという視点を持つ小川さんから見て、FinTechにはどのような意義・可能性があると感じますか?
FinTechを通じて実現する世界では、従来の銀行がなかなか手を差し伸べにくいスモールビジネスの方々も金融サービスを享受できるようになります。これは既存の銀行サービスと対立するのではなく、共存することで社会全体への貢献に繋がると信じています。
―弥生にジョインした決め手はなんでしたか?
今のフェーズがすごく面白いなと思って、すぐにアプライしました。実は昔弥生と同じ六本木ヒルズで働いていたんです。(編集部注:2005年~2007年 に六本木ヒルズにオフィスがありました)その当時、金融の領域ではスコアリング融資(会計データを元に企業をスコアリングして融資する)がトレンドとなっていて、弥生は主要な登場人物になるという認識を持っていました。海外で話題になっていたオンラインレンディングを弥生(当時はアルトア株式会社)で先んじて実現していたり、Misocaがクラウド請求書発行サービスとしてフリーミアムモデルでスタートしたり……。チャレンジ精神を感じ、日本にFinTechの潮流が来た頃から注目をしていました。
また、FinTechサービスはリスクアセットを積み上げるものです。以前の会社で学んだことのひとつに「会社の体力に合わせたチャレンジをする」というものがありました。企業が成長するためには、新規事業への投資のようなチャレンジが必要ですが、同時に自己資本に見合った範囲に収めないと会社が傾いてしまいます。前職のリクルートのような時価総額で上位5本の指に入るような企業とは異なったチャレンジ方法になることも自分の能力を発揮し、弥生のお客様へFinTechをご提供できるチャンスだと思いました。
FinTechとは顧客のペインを解決するもの
―FinTechイノベーション部長としてのミッションを教えてください。
ミッションとして、弥生のお客さまにお金の流れをもっとスムーズにするFinTechサービスをお届けしたいと思っています。金融サービスにはいろいろなルールがありますが、先行者たちが培ってきたルールの整理やビジネスモデルをうまく取り込みながら育てていきたいと考えています。

―今後の具体的な展望やビジョンはありますか?
今年の6月には請求書の即日支払いサービス「フリーナンスfor弥生ユーザー」、9月には「弥生 請求書カード払い」をリリースしています。どちらも短期的なキャッシュフロー改善につながるサービスですが、今後は業務改善や生産性向上のためのFinTechサービスを展開していこうと考えています。
―個人的に、FinTechとは主にキャッシュフローに関わるサービスを指すイメージでした。業務改善にも寄与するんですね。
はい。FinTechとは文字通りファイナンス×テクノロジーです。ファイナンス文脈では、突発的なキャッシュフロー不足を改善するとともに、テクノロジー文脈では経理の永遠の課題である消し込みや振り込みデータのアップロード業務など、まだまだお客さまのペインが残っています。こうしたペインを、例えばBaaS(Banking as a Service)を活用した銀行サービスへの参入し、業務ソフトと連携したバックオフィス業務の省力化を実現していきたいと考えます。
「弥生のお客さま」ならではの優位性をサービスへ
弥生のお客さま=スモールビジネスと銀行という組み合わせで言うと、銀行口座の開設がしづらいというのは非常に大きなペインになっています。弥生を通じて、それを基本オンラインかつ最短即日完結できるようなサービスを提供していきたいと考えています。
我々がやる意味、我々として提供できる価値のひとつとして、「弥生のお客さまという信用」があります。弥生のお客さま、すなわち弥生製品を使っているということは、その会社の取引やお金の流れが実体として記録されているわけです。口座開設のシーンにおいて銀行側はマネーロンダリングや口座の売買に目を光らせているのですが、弥生のお客さまであるということがひとつの信用となりえます。
先ほど話した請求書即日払いサービスと請求書カード払いは手ごたえを感じています。弥生のお客さまはこういった新しいサービスにご興味をお持ちで、そして反応が早い。これは他社に比べても特徴がある部分と思います。
また、今後データの活用という点でも独自性、優位性を出せると考えています。弥生の製品をご利用いただくことで、財務データだけではなく商取引や給与のデータも蓄積されていきます。これらは適切に保護しながらAIも活用をすることで、たとえばその会社が今後得られる収益や支出など、経営者にとって重要な経営情報が有用な形で伝えられる世界を実現できるでしょう。
目指すのはお金にまつわる煩わしさから解放され、プロフィット部分にリソースを割ける世界
―展望をお伺いしていると、将来的に弥生を使いこなす人はより生産性が高くなる可能性があるということでしょうか
そうですね。中小企業白書では、この10年間で生産性を1.5倍にしていかなければならないと言われています。さらに20年後で言えば2.5倍に。過去20年で生産性が変わっていないのに、ですよ。ですから、弥生FinTechの使命はスモールビジネスの生産性を上げることになっていきます。
先ほど挙げたバックオフィス業務のうち、お金に関する業務の圧倒的な省力化を実現するためには、業務ソフトとの連携したUI/UXの改善が重要になると考えています。
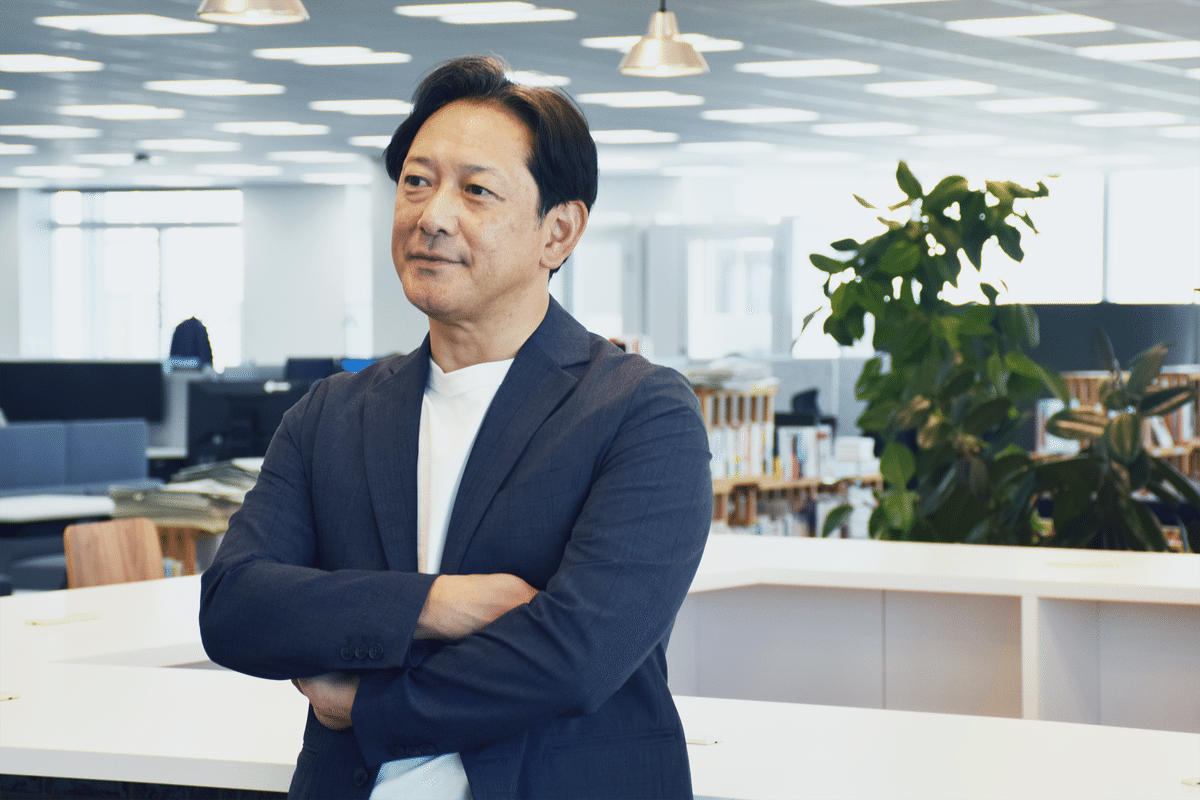
プロフェッショナルとして、責任と権限をセットに
―FinTechイノベーション部はやりたいこと、やるべきことが山積みな印象を受けました。チームとしては今どこにフォーカスを置いているのでしょうか?
まずはプロダクトを早くリリースしていくことだと思います。
―プロダクトの早期リリースでいうと、FinTech関連サービスは弥生の中でもかなり速いペースで検討とリリースが進んでいると感じています。秘訣はありますか?
まず、FinTechイノベーション部に所属するメンバーは非常にプロフェッショナルな人材ばかりです。業界に精通した人、新規サービスの開発経験がある人、弥生の経験が長い人――それぞれの得意分野をうまくミックスして相互補完していますね。
―たしかに、FinTechイノベーション部は特にプロフェッショナル人材の集まりであるというイメージがあります。その長として、小川さんがメンバーに伝えていることはありますか?
いくつか重要なことがあるのですが、1つ目はプロフェッショナルとして、数字や納期にこだわりを持ってほしいということです。成長をしてほしいし、成長をするための挑戦をしてほしい。2つ目は、人に対してリスペクトを持ち、オープンマインドで関係性を築いてほしいです。疑問に思うことは言ってほしいし、質問やアドバイスされたら聞いてほしいと伝えています。個人ではとても優秀だけど、この2点が弱い人はプロフェッショナルだとは思えません。
―さまざまな企画が並行していますが、それぞれメンバーが一人で責任を持って担当しているのでしょうか?
責任と権限をセットとして、一人のメンバーにPdMとして中心に立ってもらっています。ただ、壁打ちなどで私や他の歴が長いメンバーがサポートしています。FinTechという領域においては私も10年やってきたので、歴史的な背景の理解も含め、力になれると思います。あとはマルチプロジェクトのマネジメントはメーカーの時の経験が活かせていますね。
―独立するプロフェッショナルなメンバーが揃う中で、FinTechイノベーション部長としての役割は何になるのでしょうか?
全体最適を図ることでしょうか。新規事業というのは社内の既存リソースを使いづらい場面が多くなるものです。私はFinTechイノベーション部長として、そして執行役員のリーダーシップチームの一員として、ワンチームで会話し、課題があったら助けあうという関係性を築くことが重要です。リーダーシップチームの関係値も非常によく、マーケティング、セールス、開発部門、コーポレートなど、いろいろな相談がしやすい関係になっています。
製品開発部門にはサービスロードマップに基づいた開発ロードマップがあります。それぞれの納期がある中でこれから我々はサービスを作ってと依頼する側となることが多いですが、意見を交わしながら「こういうUI/UXにしよう」とすり合わせをしていきたいですし、それができる関係性が築けているのではないでしょうか。
―最後に、弥生のお客さまに向けたメッセージをお願いします。
ぜひ、どういうお悩みがあるのか、特にキャッシュフローやお金の請求・支払い事でのペインを教えてください。弥生はそれを解決できるサービスを提供し、弥生のお客さまの生産性が上がるようなお手伝いをしていきたいと考えています。
📨キャッシュフローやお金の請求・支払い事でのお困りごとを教えてください。

編集後記
小川さんの愛読書はビジネス書が中心。ノウハウや理論も好きですが、特に実際の経営者たちが向き合ったハードシングス(明確な解決策が存在しなかったり、大きなリスクを伴う状況)をよく読まれるそうです。ちなみに本は紙派。その理由は三人いるお子さんがいつか手に取ることも考えてのことだそうで、こんなところにも事業を作るだけでなく続け、育てていく小川さんらしさを感じられました。

