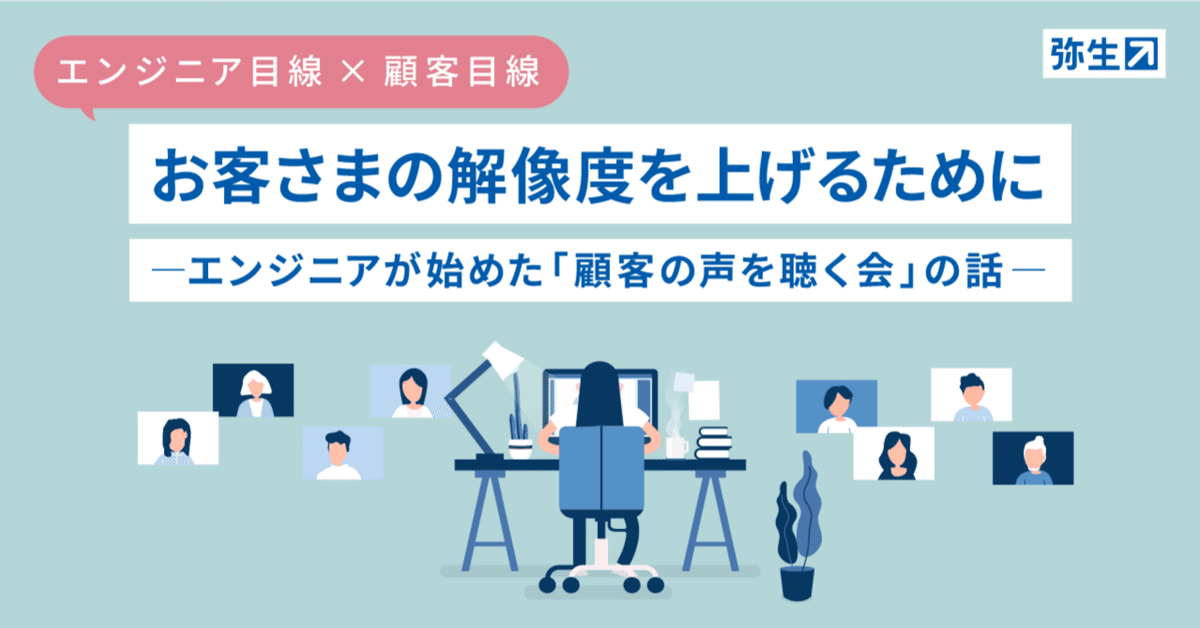
お客さまの解像度を上げるために—エンジニアが始めた「顧客の声を聴く会」の話—
弥生では、お客さまからいただいた声を社内で共有し、より良い製品やサービスづくりに役立てています。その一環として、開発チームでは「顧客の声を聴く会」を開いています。この会では、カスタマーセンターに寄せられた実際の電話録音データをもとに、お客さまのリアルなお問合せやご要望を聞き、改善点や感想を話し合っています。
今回は、主催するエンジニアのOさんに、この活動を始めたきっかけやチームの変化についてお話を伺いました。
お客さまの目線で考えられるように

ー「顧客の声を聴く会」は、どのようなきっかけで始まったのですか。
新卒時に業務と研修の一環として、2か月間、年末調整時期の電話対応を経験しました。お客さまの声を聴き、お困りごとを知ることができ、大変勉強になりました。
チームのメンバーにもこの経験を共有したいと思い、2023年の10月から「顧客の声を聴く会」を始めました。これまでに12回開催しています。
ー「顧客の声を聴く会」は、どのような目的で行っていますか。
お客さまのお困りごとを知り、製品を改善するために何をするべきかを、エンジニア一人一人が考えるようになることを目的に始めました。エンジニアは普段お客さまと接する機会が少ないので、お客さま目線で主体的に製品開発ができるようになりたいという願いがあります。
ー実際にどのような活動をしているのですか。
カスタマーセンターから共有されたお客さま対応音声を聞きながら、チャットで気づいたことや感想をコメントしています。その後、皆で気づいたことなどをディスカッションしています。活動はオンラインで、20人ほどが参加しています。
取り上げるテーマは、会計ソフトの基本的な機能についての改善要望などが多いです。また、ベテランの方から過去の経緯を聞き、理解を深める機会もあります。印象的だったのは、帳簿の仕訳をExcelファイルに書き出す機能についてです。一見シンプルな機能ですが、実は複雑な技術的制約があることを、ベテランの方との話を通じて知りました。

ー実施する時に、気をつけていることはありますか。
本質的には製品改善につながることを目的としていますが、そのためにはメンバーが主体的に取り組める環境を作ることも大切だと考えています。 そのため、お客さまから寄せられた嬉しい声や熱意ある改善要望を共有し、どうすれば製品をより良くできるかを一緒に考えられるように意識してファシリテートしています。また、毎回メンバーから会全体に対するフィードバックをもらい、運営方法を少しずつ改善しています。
ー運営方法の改善とは、どのようなものを行ってきましたか。
当初は、音声のみを共有していました。でも、音声だけでは、お客さまの状況を想像が難しいというフィードバックをもらい、私がお客さまのお手元の状況に合わせて製品操作を行い、その様子を画面共有するようにしました。具体的にお客さまが何を行っているのか、メンバーは想像しやすくなりました。
声を聴くことでお客さまの解像度が高くなる

─印象に残ったエピソードはありますか。
「仕訳重複チェック」という機能について、こんな使い方をしたいという要望があったのですが、私たちが想定していた使い方から一歩踏み込んだ内容で、エンジニア一同、目からうろこでした。元々、改善を重ねる前提でリリースしていましたが、お客さまの声を受けて、次の改善に向けてさらに検討しているところです。
また、90歳のお客さまから確定申告書の作成に関するお問い合わせをいただいたことも印象に残っています。生の音声を聞くことで、幅広い年齢の方にご利用いただいているということが実感できました。
─会に参加したメンバーからは、どのような反応がありましたか。
「毎回新たな発見がある」「ユーザー層の広さに驚き、人物像が見えたことでモチベーションが上がった」「製品だけでなく、サポートを含めて弥生だと実感した」という声がありました。また、担当外の製品の機能を学べたり、ベテランエンジニアから知見を得る場にもなったとのことです。
─日々の業務への影響はありますか。
エンジニアが要件定義と呼ぶ、製品改善の具体的な内容を決めていく作業の中で、お客さまがどのように製品を使うのかを考えながら進めることができるようになったと聞きます。
─今後、「顧客の声を聴く会」をどのように活用していきたいと考えていますか。
エンジニア一人一人に与えられている10%の改善活動の時間を、お客さまの声を反映することに使えないかと検討しています。
弥生の製品は、お客さまが普段の業務を効率化するために使うものなので、お客さま中心であるべきです。お客さまの期待に沿った製品を提供するために、ズレが減るように取り組んでいきたいと思っています。
さらに、今年1月に開発本部で「お客さま目線を考える」プロジェクトが発足しました。私がリーダーとなり、本部のメンバー全員が顧客目線を醸成する取り組みに参加できるよう進めています。今後は「顧客の声を聴く会」の活用方法も含め、より広くお客さまの声を製品開発に反映できる仕組みを検討していきます。
弥生全体でお客さまのニーズをとらえた製品開発ができるよう、今後も頑張っていきます。
編集後記
Oさんは、「顧客の声を聴く会」の他にも、CS本部メンバーとの交流会を実施し、チームメンバーがエンジニア目線と顧客目線を持てるよう取り組んでいます。この取り組みがチームや製品改善にも良い影響を与えていると評価され、FY24チームヤヨイ賞を受賞しました。
私も「顧客の声を聴く会」に参加してみましたが、お客さまの生の声を知ることができました。メンバー同士で飛び交う活発な意見も良い雰囲気でした。今後も、お客さまの声を活かした取り組みが進んでいくのが楽しみです。

